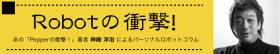東京・渋谷に居を構えるアート施設、シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]で『Embodiment++』という展覧会が開催されている。
東京2020 パラリンピックやWBCのオープニングセレモニーでの光の演出。阪神タイガース「ウル虎の夏2023」にて、ドローンに吊り下げられたLEDフラッグに六甲下ろしを映し出す演出で話題となった、直接的に名前は知らずとも多くの方が作品を知っているであろうクリエイティブカンパニー、MPLUSPLUS株式会社による展覧会だ。
その展示作品のなかで、人間不在の巨大ロボットによるパフォーマンス作品が密かに話題になっている(下の動画を参照)。
今月19日まで開催される会期の中で、様々なワークショップやトークセッションが積極的に開催されてきたが、その中で特に注目すべきイベントとして9/29に開催された、東京大学教授の稲見昌彦氏とMPLUSPLUS代表 藤本実氏とのトークセッションを抜粋してお伝えする。
会期:2023年9月16日(土)〜11月19日(日)13時~19時※月曜休館(祝日の場合は開館、翌平日休館)
※会場でのロボットアームによるパフォーマンスは期間中、観覧できるが最終上演は18:45
開催場所:CCBT
住所:〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町3-1 渋谷東武ホテル地下2階
公式サイト:https://ccbt.rekibun.or.jp/events/mplusplus-embodiment
主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]
二人の表現者/研究者
イベントは二人の自己紹介、そしてこれまでに制作してきた作品の紹介から始まった。
藤本実氏はHMDを常時装着していることから「ウェアラブルコンピューティングの伝道師」と呼ばれる神戸大学の塚本昌彦教授の研究室出身。自身のライフワークであったダンスとウェアラブルコンピューティングを結びつける研究をしていた。
その研究をメディアアートの世界的祭典、「アルスエレクトロニカ」にて発表、IPA未踏にてスーパークリエイターとして認定されたことをきっかけに、国内外のエンタメ業界でトップクリエイターとして認められ、藤本氏の作品制作は徐々に加速していく。
■”Lighting Choreographer” contemporary dance ARS ELECTRONICA 2010
■LED VISION FLAG
■WAVING LED RIBBON / Opening For The Brighter Future
アジアデジタルアート大賞を受賞
そして、これらの作品群の制作のなかで転機を生んだのはクライアントワークを離れ、個人制作した光の巨人、Humanized Lightだ。
身体性を持った光を演者にまとわせて踊らせるという藤本氏独自の感覚を人を介在させることなく空間に拡張したこの作品は、アジアデジタルアート大賞を受賞。Taiwan Technology X Culture Expoにも出品した。
ライブエンタテイメントやダンスの文脈の中で常に人の体と向き合ってきた藤本氏。この作品を通じて「人間がいなくても、機材やデジタル技術だけで身体性や躍動感を表現できる」という自信をもてたことが今回のCCBT展示へと繋がったのだという。
■Humanized Light
そして、CCBTでの3つのロボットによる作品。これらは写真や動画では魅力を伝えることが難しい作品なので是非会場にてご覧になっていただきたい。
巨大なロボットが、速く正確に踊ることによって人間の動きの更新を狙う「Morphing Elegance ーRobotic Choreographer」

写真提供:シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]、Photo courtesy Civic Creative Base Tokyo [CCBT]
LED WAVING RIBBONの極限の柔らかさによって生まれる「デジタル技術で生成された有機的な気配」をシンプルな構造のロボットとLED WAVING RIBBONのインタラクション、そして精妙極まる光の演出で表現した「生命感を持つ光」Vitality of LightーLight-emitting Existence。
(この作品だけは本当に写真や動画で伝えることは難しい。実物をぜひ見ていただきたい)
BPM160で構成される異形のダンスミュージック「シカゴフットワーク」を軽やかに踊りこなす時計型ロボットUnknown RhythmsーHumanized Clock

このようにテクノロジーの力によって人間の身体感覚を挑発するような作品が並ぶ。
これらの作品づくりをささえる基盤は「MPLUSPLUS」という藤本氏が代表を務める会社の開発力だ。
師、塚本昌彦氏の遺伝子(Mは塚本昌彦氏の頭文字)を拡張させていくという思いを込めたこの会社は、スタッフの半数が博士号を持ち、クライアントワークをこなすだけでなく、あたかも大学の研究室のように各人個別のテーマの開発を進めている。
新しい物を作れば作るほど解決すべき問題が生まれるという循環の中で「膨大なプロトタイピングのなかから正解を掴み取る」という新たな開発スタイルも貪欲に取り込み、藤本氏は現在進行形でMの遺伝子を拡張し続けている。
表現する研究者、稲見昌彦氏
それに対して稲見氏もVR研究の黎明期から活動する名門、東大の舘暲名誉教授の研究室出身。
塚本氏と藤本氏のちょうど中間年代にあたる稲見氏は下図のように黎明期から続くVRの研究を受け継ぎながら、自身のカッティングエッジな研究を続けており、さらにその教え子達の研究も様々な分野へと応用が期待されている。

稲見氏の研究衝動の結晶である「作品」は「SIGGRAPH」(国際的なインタラクション、CGに関する国際会議、展示会)の査読付き実演展示:Emerging Technologiesに出展したものだけでも50を超える。そのなかでも特徴的な作品をいくつか挙げてみよう。
■TWISTER: a media booth – SIGGRAPH 2002 Emerging Technologies
■Stop Motion Goggle
スポーツの連続写真の撮影などにも使うマルチ発光ストロボのような効果により動態視力を向上させることができる。
また、シャッターの動作周期や左右の位相差を調整することで、人間が知覚できない「動作周期」などの変数を「時間」や「空間」へと変換することができるなど、「使い込むごとに気づきを得られる」ニューメディア開発の醍醐味のような作品。
近年の稲見氏はこれらSIGGRAPH出展作品のような「新たなメディアを作る」研究と同時に、「新たなメディアをどう使うか」「新たなメディアがどのようなコミュニティを生むのか」に対しても興味を広げている。
その研究プロジェクトの一つ、「けん玉できた!VR」は「時間の流れが遅い仮想空間」の中で練習することで現実世界の動作の難易度を調整できる作品だ。
■けん玉できた!VR
このシステムを使うことで、正しい成功と失敗のフィードバックを得て高速でけん玉の習得ができるのだという。
VRといえば、いかにホンモノらしく世界を作ることができるのか、に苦心していたわけだが、仮想空間が現実に沿うことにこだわる必要はないということに気付かされる。卑近な例を挙げると、転職することで急に結果を出せるようになる会社員を見ればわかるように、その世界のルールによって人間が発揮できる能力は変わる。
「人と間(世界)を拡張していくことで新たな能力を発揮できるようにすることが人間拡張である。『多様なルールを持つ世界』を創造することの意義がわかってきた。」と稲見氏は語る。
■6th Finger Project
六本目の指をつくるという作品も「多様性」を感じるものだ。六本めの指を使ったワークショップを体験する子どもたちが新たに手に入れた指をデコり始めたという体験から、本来あった身体の欠損をホンモノに近い物で補うことを至上とする「義肢」の世界と、本来なかった身体を獲得していくなかで多様な外見をも認める「人間拡張」との違いを強く感じたのだと言う。
エンタメの力と共感チャンネルを使ったサイエンスコミュニケーション
このような先端的な研究を数多く行う稲見氏は、東京大学総長特任補佐 先端科学技術研究センター副所長という重責を務めている。
研究と同時にその成果を世間に対して知らしめていく責任も負う稲見氏は、サイエンスコミュニケーションのやり方に、「藤本氏を始めとする塚本研のアプローチ」の強い影響を受けたのだと語る。
■自在化コレクション -Jizai Collection / Full Version-
その集大成が2022年に開催されたERATO「身体自在化プロジェクト」の最終報告会だ。能、攻殻機動隊を始め、シアターを借り切っての前代未聞の報告会。エンターテイメント、パフォーマンスの要素を取り入れた研究報告会は、テクノロジーに興味のない層にも研究成果の先にある世界を広く伝えることを狙ったものだ。
このスタイルは「ウェアラブルコンピュータ」の進化を「ダンス」というエンタメにのせて一般層に広く伝えた藤本氏の活動を参考にしたと稲見氏は言う。
シアター、ガジェット、スポーツなどのエンタメの力を借り、一般層を「研究成果のもたらす新しい世界」に共感させることで、見るものの心を動かす。このことが、未来に向けて踏み出させる、新しい形のサイエンスコミュニケーションなのだ。
アルスエレクトロニカを始めとする「表現の世界」への稲見氏の進出も、この「共感チャンネル」のエンジニアリングという切り口で見ると新たな気づきが感じられるのではないだろうか。
■自在肢 | JIZAI ARMS: SOCIAL DIGITAL CYBORGS (short ver.)
それにつけても感じるのは、稲見氏、藤本氏のような先端の研究者たちの「新たな知見を取り入れる能力の高さ」だ。
これらの作品や表現のスタイルの幅広さは、それぞれ、舘研、塚本研という名門研究室の流れを受け継ぎながら、専門分野や年代の違いにとらわれず常に他者と関わり、自己のスタイルを更新し続けていることをうかがい知ることができる。
身体感と人間拡張とは
この二人の興味を集める「身体感」やその拡張とはどのようなものなのだろうか。その答えの一端をトークセッションの後半、稲見氏による藤本氏の作品への講評から探ってみよう。
まず、講評の俎上に上がったのが、藤本氏の転機となった個人作品「Humanized Light」だ。光は物質と情報の両面を持つと言われるが、スポットライトの動きを中心とした空間から、その物質性を強く感じさせた光の巨人。

強力な光量を持つスポットライトは、その光の到達距離が長ければ長いほど、回転運動をした際の終端速度が増す。
理論的には、巨人の脚の速度が光速を超えているかのように見える「物質としてはありえない動き」ですらHumanizedLightであれば表現できる可能性がある。と稲見氏は語る。
ここには、藤本氏の演出による、音、動きのプログラミングと光の演出がマッチしたことで感じられる物質性、あるいはそこから感じられる有機的な身体性が大きく寄与していることは言うまでもない。
そして、このような物質性、存在感がもたらす肉体的な脅威が人の心を動かす「感動」に大きく寄与しているのだという。
次に講評されたのはリボンとLEDを使った作品、Vitality of LightーLight-emitting Existenceだ。
稲見氏はこの作品の表題にもある「生命感(Vitality)」について強く言及した。
ディスプレイに光点が増えることと暗闇に小さく灯る光の粒。
網膜に映る視覚情報はそう変わらないように見えるが、実際に人間が受ける心象は大きく異なる。ましてそれが人体のような、人間にとって強い存在感を持つものであれば大きな衝撃を与えうるはずだ。

最初期の藤本氏の作品、光る衣装を着て舞い踊る作品Lighting Choreographerから稲見氏が受けた感動は、「身体の一部」というsense of embodimentを感じさせるオブジェクトが光の明滅によって人体の運動限界をこえ、物理限界すらも超えた動きをしているようにみえたことによるものだったという。
そのsense of embodimentが抽象化され、凝縮されたのが一粒のLEDを光らせているVitality of LightーLight-emitting Existenceだ。
極限のしなやかさを持つリボン素材のLEDがシンプルな等速回転運動と交わることで生まれる不可測な動き。これにさらにLEDの光の明滅が加わることにより、たんなる光の粒に、生命の息吹を感じさせる。
このsense of embodimentを感じさせる光の粒が藤本氏の光の演出によって質量を有する物質の限界を超え、気まぐれに宙に舞う妖精のように自由に振る舞う。
最初期においては人体、という具象的な素材を用いていたことが、10年を経てここまでミニマルなもので表現できるようになる。ここに至るまでの藤本氏の積み上げには脱帽するしかない。
Choreographerとしての次のステップへ
しかし、そこまで積み上げた「光の魔術師」ともいえるような表現手法をあっさりと打ち捨てたように見えるのがもう一つの新作Unknown RhythmsーHumanized Clockだ。
時計を模した長針、短針それぞれ一自由度のシンプルなロボットが160bpmという驚異的スピードで展開されるダンスミュージックに合わせ、時計盤面というステージの上を踊り回る。

撮影:加部壮平、Photo: Kabe Sohei [敬称略]
写真提供:シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]、Photo courtesy Civic Creative Base Tokyo [CCBT]
このロボットにおいて、光という武器をあえて取らずに制作した狙いは何なのだろうか。
稲見氏が、作品を見た誰もが感じていた疑問、「光の魔術師が完全なる物理の世界に降りてきた理由」を問うと、藤本氏は「もともと移動を表現するのに最も楽だったから光を使っていただけなんですよ」と事もなげに答えた。
そしてChoreographer(振付師)として「新しい動き」を純粋に作ろうとしているのだ。と。
それが今回の新作、Unknown RhythmsーHumanized Clockなのだそうだ。
光でできる表現の限界をVitality of LightーLight-emitting Existenceのような作品でつきつめてしまった今、完全なる物質だからこそできる躍動感の追求に新たに興味がわいてきたということなのだろうか。
たしかに、バレエや新体操のような「まるで体重を感じさせない動き」には質量を持たない光の表現が向いているだろう。
そして、コンテンポラリーダンスのような重みの表現や、ブレイクダンスの弾けるような動きは物質のもつ存在感あってのものなのかもしれない。
しかし選んだジャンルがシカゴフットワークとは。
■HOW TO DO CHICAGO FOOTWORK
BPM160という人間ではとても踊ることができないような楽曲。それを踊り切れる運動性能を持つロボットを作ることで、私達はなにを感じさせようとしているのか。
藤本氏はそれを具体的に一言であらわしはしていなかったが、「人間の身体の持つ可能性」への気づきをロボットの表現を通して促してるようだ。ロボットと人間の違いはあれど、明滅によるトリック的なものではなく、物理法則に縛られた動きを見ることで生まれる気付き。
Humanized Clockの短針は「この短針にできる表現であれば、人間の体でもできるのではないか。」という気づきを脳に促すよう、人間の腕よりやや長い程度のサイズになっているのだという。

将棋AIから学ぶことで藤井聡太氏が爆発的なパフォーマンス示しているのと同じく、人間以上のダンサーHumanized Clockのパフォーマンスから次代のスーパーダンサーや新しいダンス表現が生まれることを期待したい。
なお、今回の対談の中で稲見氏から藤本氏にHumanized Clockの強力な運動性能を持ってリアル「分身の術」のような残像表現を是非してみてほしいとの要望があった。会期が終わるまで作品のブラッシュアップをつづけるという藤本氏はこの要望に応えるつもりのようだ。ぜひ一度CCBTを訪れた方も新たに見に行って作品の違いを感じてみてほしい。
むすびに -先端と最新と人間拡張-
今回の対話は、一流の研究者であり、表現者でもある二人だからこそ生まれた素晴らしいセッションだった。
しかし、一流の研究者でも表現者でもないシビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]に集う市民はクリエイティブであるために、ここからいかなる学びを得るべきなのだろうか。

写真提供:シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]、Photo courtesy Civic Creative Base Tokyo [CCBT]
そこに稲見氏、藤本氏はイベント最後の質疑応答の中でこの施設にふさわしい答えを与えてくれた。
二人は
「最先端であることは最新鋭であることを必ずしも必要としない。」
「テクノロジーがどうだということにはこだわっていない」
のだという。
「前例がないこと」を重視するアカデミックな研究分野にいてさえ、レトロニム(この場合は先端技術が生まれたことにより旧来とは違う価値が再発見されたもの。例としてはカラー写真が生まれたことで、詩的側面に注目された白黒写真など)に注目する稲見氏。
表現の新しさを追い求める中で、最新であるかにこだわらず様々な技術や素材を取り入れる藤本氏。

常に時代の変化に目をみはっていれば、新たな物、古くからある物に、等しく新しい価値が生まれつづけていることがわかる。
それを利用することが、「人」と「間(世界)」の変化によって生まれる「人間拡張」の一つの形なのかもしれない。平凡な一市民として、クリエイティブな姿勢を取り続ける勇気を得ることができた気がするイベントだった。