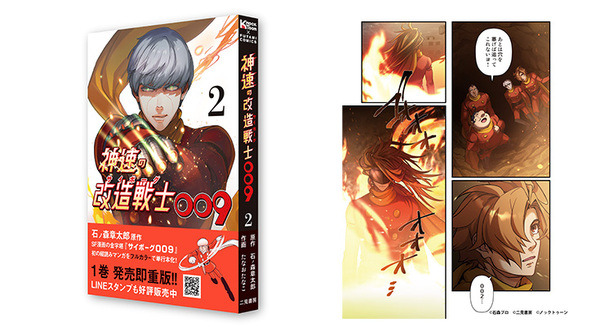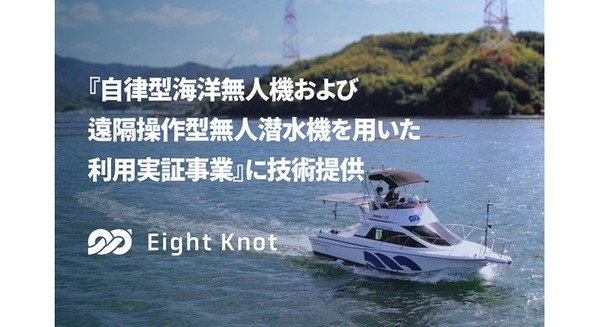京都橘大学はAI研究者である松原仁教授が取り組むプロジェクトをまとめた特設サイト「ヒトシの部屋」を公開した。
人とAIで手塚治虫の“新作漫画”を制作した「TEZUKA2020」や、AI作家による小説で星新一賞の入賞をめざす「きまぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」、自律移動型ロボットの国際競技会「ロボカップ」の創設など、ユニークなプロジェクトを通して、AIロボティクスの面白さ、未来の可能性を伝える内容となっている。
「ヒトシの部屋」とは?

京都橘大学は2026年4月、工学部ロボティクス学科、デジタルメディア学部、健康科学部 臨床工学科の新設を予定している。「ヒトシの部屋」はAI研究者でもある松原仁教授が「AIロボティクス」の面白さ、未来の可能性を対談やコラム、動画などをさまざまなコンテンツを発信する特設サイト。
今回は、東条湖おもちゃ王国撮影協力の下制作したキービジュアルのほか、これまで進めてきたユニークな研究・プロジェクトを、将棋・小説・漫画・ゲーム・スポーツ・観光の6分野の視点から紐解く記事を6月6日に公開。子どもから大人まで幅広い年齢層の好奇心を引き出し、楽しませる場所「遊園地」をコンセプトに、AIロボティクスの楽しさを伝えるとしている。
松原ヒトシのPROJECT 概要
PROJECT01 『将棋』

松原仁教授が大学に入学した頃はまだパソコンが普及しておらず、AIの教科書もほとんどなかった時代。「将棋の名人に勝つプログラムを作る」という目標を掲げて研究を始めたが、初めは「めちゃくちゃ弱かった」とのこと。人間をはるかにしのぐほど強くなるまでには、どのような道のりがあったのか?
PROJECT02 『小説』

松原仁教授は、30冊を同時並行で読んだ時期があったほどの本好き。コンピューター将棋の研究の後に選んだテーマのひとつが小説だった。AIに小説を書かせて文学賞に応募するという取り組みは大きなニュースになった。急速に進歩を遂げるAIが直木賞を受賞する日も、そう遠くないと考えているとのことだ。
PROJECT03 『漫画』

4歳で出会った『鉄腕アトム』に魅せられ、「いつか鉄腕アトムを作りたい」と夢を描いてきた松原仁教授。アトムを生み出した漫画家、手塚治虫の漫画をAIに学ばせて新作をつくるプロジェクトに取り組んだこともある。そこで改めて手塚作品のすごさを感じたのだとか。松原先生、『鉄腕アトム』の新作ができるとしたら何年後になるのか?
PROJECT04 『ゲーム』

松原仁教授はロボットにサッカーをさせる「ロボカップ」創設者の一人として草創期から関わり、ゲーム情報学研究会の立ち上げメンバーでもある。大学生の頃に研究を始めた将棋もゲームの一種ですが、実は、日本では長くゲーム不遇の時代が続いたそうだ。周囲の理解を得られない中で、どのように研究を続けてきたのだろうか?
PROJECT05 『スポーツ』

松原仁教授は長らく、将棋や小説、漫画など「AIに何かをさせる」研究をしてきた。でも最近は、人間がスポーツをする時にAIがどのように役立てるかについて考えているとのこと。スポーツの世界にAIが浸透することで、スポーツの楽しみ方も変わっていくのだろうか?
PROJECT06 『観光』

松原仁先生は旅行も好きで、今は「AIでオーバーツーリズムをどう解決できるのか」に頭を悩ませているとのこと。「めちゃくちゃ難しい」と話しつつ、新しい難題に向き合うことが楽しそう。オーバーツーリズム解消の困難さの理由や、AIを用いて社会課題を解決することについて話を聞いた。
松原仁 教授 プロフィール

東京大学大学院情報工学専攻博士課程修了。工学博士。
通商産業省工業技術院電子技術総合研究所(現 産業技術総合研究所)、公立はこだて未来大学教授、東京大学教授を経て、2024年4月より京都橘大学教授。専門は人工知能。ゲーム情報学、観光情報学研究に取り組む。
人工知能学会元会長、情報処理学会前副会長。人とAIで手塚治虫の”新作漫画”を制作した「TEZUKA2020」、AI作家による小説で「星新一賞」入賞をめざすなどユニークなプロジェクトを多数手がけている。2026年4月より、工学部ロボティクス学科教授(予定)。