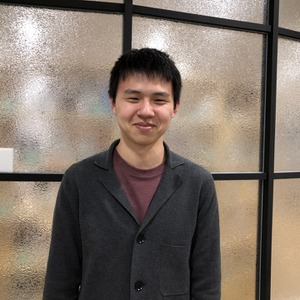株式会社メルティンMMI(以下、MELTIN)はENEOS株式会社とアバターロボット「MELTANT」シリーズの活用に向けた実証実験を実施したことを発表した。
試験分析作業にフォーカスした実証実験
プラント等での危険を伴う作業や健康リスクを伴う作業のロボット化・リモート化を念頭に、今回は製油所に隣接するENEOSの中央技術研究所において、試験分析作業をアバターロボット「MELTANT-β」(メルタント・ベータ)により遠隔化する実証実験を行った。
ENEOSの中央技術研究所では石油製品の分子構造解析や組成解析などを通し、製油プロセス改善や品質向上などの燃料研究・開発、潤滑油や機能化学品材料などの高性能製品の開発を行っている。このような研究開発の場では人が試行錯誤しながら、様々な分析装置を駆使して多種多様な試験や分析作業を行う必要がある。そのため、全ての作業内容を規格化することが難しく、劇物や毒性物質を扱う場合であっても、人間が作業にあたらなければならないことがある。この作業現場でMELTANT-βの使用が期待されている。
人と同等の高い自由度のハンドを持ち全身が人と同じサイズに設計されているMELTANTシリーズは、研究者の利用している既存の器具や設備を専用に改修することなく利用できる。また、操作者の動きをそのまま再現し、あたかもその場にいるかのように作業に当たることができるため、操作法を長時間かけて覚える必要がなく、初めて操作する人でもある程度の作業を行うことができる。今回の実証実験はENEOSの研究者が実際にMELTANT-βを操作し、多様な実験作業の検証を行った。

ビーカー内の液体をメスシリンダーに注いで取り分ける
各種実験装置へ検体をセットする
カートを操作しながら運搬をする
ドラフトチャンバーのシャッターを開閉する 等
プラント施設全体での活用に向けて今後も研究開発を実施
今回は試験分析作業にフォーカスした実証実験だったが、この先プラント施設全体でのMELTANTの活用に向けて、継続した研究開発を実施することにより、様々な社会課題の解決を図っていく。主に利用が想定されるシーンは下記の通り。
・特殊技能/知識を有する作業員による遠隔地からの対応(希少人材の複数拠点での同時展開)
・自動化を組み合わせた省人化(労働人口不足の解消)
なお、今回の実証実験ではワークショップを同時開催し、MELTANTが製油所や研究所でどのように活用できるかについて、体験を踏まえてディスカッションした。
アバターロボットとサイボーグの現状と未来「国際サイボーグ倫理委員会」(GCEC)キックオフイベント
メルティンMMIがアバターロボット「MELTANT-β」(メルタント・ベータ)を発表 粉塵や火花の散る環境で働く動画を公開
「アバターロボット保険」三井住友海上とMELTINが保険開発に関する協業 遠隔操作ロボット実用化に向け2020年より実証実験実施
メルティンMMI関連記事
株式会社メルティンMMI