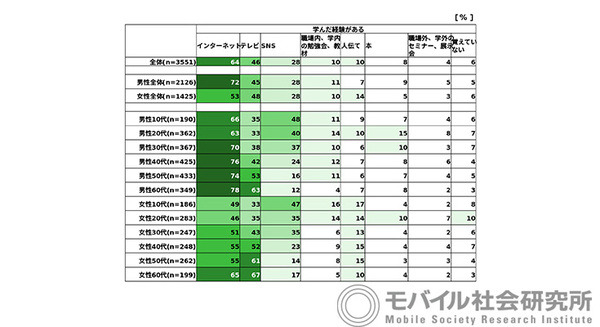GMOインターネットグループで、インターネットリサーチ事業を展開するGMOリサーチ&AIは、保有する国内モニターパネル「JAPAN Cloud Panel」のモニター1,172人を対象に、「AIトレンドに関する自主調査」を実施した。
本調査は、AIに対する理解を深め、より多くの人がAIを活用し、社会の発展に寄与することを目的とした定点調査です。2023年11月に開始し、今回で6回目となる。
調査サマリー
・生成AIの認知度は、過去約1年間70%前後で推移、利用率は9.0ポイント上昇
・生成AIを「利用している」層のうち、60.6%が1年前と比較して「利用が増えている」と回答
・生成AIを「利用していない」理由は「必要性を感じない」が68.0%でトップ
・業務利用率は、昨年8月からほぼ横ばい(36.9%)
・業務利用の懸念として「データプライバシーとセキュリティ」、「著作権や知的財産権の問題」が上位に
調査概要
| 調査テーマ | AIトレンドに関する自主調査 |
|---|---|
| 調査地域 | 日本国内 |
| 回答者数 | 1,172名 |
| 調査対象 | 15歳以上の男女 |
| 調査期間 | 2025年2月21日~2月22日 |
| 調査方法 | オンライン調査 |
調査結果
生成AIの認知と利用状況(2023年11月~2025年2月の比較)

生成AIの認知度は約1年間70%前後で推移、利用率は9.0ポイント上昇
生成AIの認知について、「知っている」(非常によく知っている/ある程度知っている/少し知っている)との回答は72.4%だった。前回調査時(第5回・2024年11月)の72.3%と比べて変化はほとんどなく、第1回調査(2024年2月)の71.1%からも横ばいの状況が続いている。
また、利用状況については、生成AIを「使ったことがない」との回答は57.5%だった。逆に、「使ったことがある」(日常的に使っている/ときどき使っている/ほぼ使わない)という「利用率」は、42.5%となり、約1年前の2024年2月調査時33.5%との比較では、9.0ポイント上昇していることから、生成AI利用が着実に広がっていることがわかった。
生成AIの利用時間・回数の変化と生成AIを利用しない理由

生成AIを「利用している」層の60.6%が「1年前と比較して利用が増えている」と回答
生成AIを利用しない理由は「必要性を感じない」が68.0%でトップ
生成AIの利用状況について、「利用している」(日常的に使っている/ときどき使っている)と回答した人を対象に、1年前と比較した生成AIの利用時間・回数について調査した。
「利用が増えた」(使用時間・回数が2倍以上に増えた/使用時間・回数が少し増えた)との回答が60.6%だったのに対し、「利用が減った」(使用時間・回数が少し減った/使用時間・回数が半分以下に減った)という回答はわずか2.8%にとどまった。この結果から、生成AIの利用層では積極的な活用が進んでいることがわかる。
一方で、「利用していない」(ほぼ使わない/使ったことはない)と回答した人に、その理由をたずねたところ、「必要性を感じない」68.0%が最も多く、「使い方がわからない/難しそう」が36.2%と続いた。生成AIの未使用層では、活用イメージの乏しさや使い方の難しさが背景にあることが示された。
生成AIの業務利用状況と懸念(2024年8月~2025年2月の比較)

業務利用率は昨年8月からほとんど増加していない
業務利用の懸念として「データプライバシーとセキュリティ」、「著作権や知的財産権の問題」が不動の2トップ
今回の調査では、生成AIの業務利用率(日常的に利用している/ときどき利用している/ほとんど利用しない)は36.9%と、昨年8月の36.0%からほぼ横ばいという結果となった。積極的な利用層(日常的に利用している/ときどき利用している)に着目すると、昨年8月の15.7%から今回は19.2%へと、3.5ポイントの上昇傾向が見られる。
生成AIの業務利用での懸念点としては、「データプライバシーとセキュリティ」および「著作権や知的財産権の問題」が、過去の調査結果と同様の傾向で、上位2項目となっている。これらの懸念は、生成AIが今後さらに進化し、その有用性を実感するほど、悪用のリスクや問題解決の難しさを強く意識させる性質のものだと考えられる。プライバシーや権利の保護などに対する構造的な課題の解消が今後も重要であることが示唆されている。
一方で、「雇用への影響」や「バイアスや差別の助長」といった、人間の影響力が低下していくことに対する漠然とした不安に関しては、回答率が継続的に減少している。これらは、生成AIの利用が広がり、理解が進むにつれて、不安を解消している人が増えていることを示していると考えられる。
総括
生成AIの認知度は、この1年間でほとんど変化が見られなかったが、利用率では昨年2月の第1回調査から9.0ポイント上昇した。また、積極的な利用層においては、約6割で1年前より「利用が増えた」と回答するなど、AI活用が進んでいる実態がうかがえる。一方で、未利用者の回答では、生成AIの利便性や利用法が十分に伝わっておらず、「使ったことがない」との回答が半数を超える(57.5%)など、利用者と未利用者の傾向が大きく分かれていることが示唆された。
生成AIの業務利用率は、2024年8月の調査から大きな変化は見られないが、積極的な利用層では、増加傾向(15.7%→19.2% +3.5ポイント)が見られた。
生成AIの業務利用での懸念点として、過去の調査同様、情報の保護や権利に関しての回答が高くなった。単なる理解の促進だけでは解消が難しい、構造的な課題が残っていると言える。
今後は、セキュリティや権利に関するリスクに配慮した、AIの利用環境整備を進めるとともに、未利用者に対する、生成AIのわかりやすい利用ガイドや活用事例を紹介することにより、利活用の拡大が求められる。
【ドコモ調査】「ながらスマホ」と人との交流頻度の関係を調査 ながらスマホのマナー問題がまた増加中
【ドコモ調査】中学生の「生成AI」利用が1年で倍増、親の利用率を上回る状況に 年齢層/地域別の結果も公表
【調査】鈴茂器工のロボット「Fuwarica」で盛り付けたご飯は美味しいのか?AI搭載味覚センサー「レオ」が判定した結果を発表
【調査】生成AI利用者は2024年末に1,924万人、2026年末には・・満足度第1位の生成AIサービスは・・ICT総研が利用動向調査を実施
アクセンチュアが10業界のサプライチェーン成熟度の調査結果を発表 次世代サプライチェーンを持つ企業は23%高い収益性